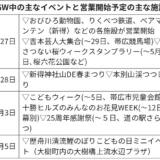コロナが変えたくらしの姿
「産む」の現場から(下)|妊婦の遠隔健診 通院減らし感染も予防


手元のタブレットで胎児の心拍数を確認しながら、コロナ感染病棟にいる妊婦と遠隔で会話する小樽協会病院の黒田敬史医師。手前のハート形の機器が分娩監視装置iCTG(打田達也撮影、写真の一部を加工しています)
「妊婦健診を自宅でオンラインで受けられたので、(外出による)コロナ感染や、車を運転するリスクを心配せずに済んだ。分娩(ぶんべん)施設から遠い場所に住む妊婦にとってのメリットは大きい」。昨年7月に第1子を出産した後志管内倶知安町の滝村和美さん(38)は、新型コロナウイルスが流行する中で受けた遠隔健診をこう評価する。
滝村さんは2016年のリオ・パラリンピックに出場した車いす陸上選手。15年前に脊髄梗塞を発症し、下半身にまひが残る。陣痛の感覚を自覚しにくいことなどから、ハイリスクのお産となる可能性が高く、地元の倶知安厚生病院から北大病院を紹介された。だが、札幌までは車で片道2時間以上かかる上、人混みによる感染への不安も大きかった。
コロナ下で、医療機関に直接足を運ばずとも、インターネットを使い、妊婦健診を遠隔で受けられるシステムの活用が全国的に広がりつつある。妊婦の通院回数を減らし、感染リスクを低減させるためだ。道内では、いち早く北大病院が20年3月、緊急的な措置として遠隔健診を開始した。
手のひらサイズの遠隔分娩監視装置「iCTG」を導入。貸与された妊婦が、自宅でおなかにハート形の器具を装着すると、胎児の心拍数や、おなかの張り具合が自動で計測される。ネット経由で送られたデータを医師が確認し、妊婦はスマートフォンなどの画面越しに診察を受ける。
滝村さんの場合、おなかの張りが分かりづらく、妊娠30週以降の約1カ月間、このシステムを使って週2回の遠隔健診を受けた。「離れていても医師と頻繁に顔を合わせて相談ができたので、安心感があった」。その後、予定通り36週で入院し、2週間後に帝王切開で出産した。
「赤ちゃんは元気だよ。大丈夫、心配ないからね」。小樽協会病院産婦人科の黒田敬史医師(42)は、iCTGを通じて手元のタブレットに映し出された胎児の心拍数のグラフを確認しながら、コロナ感染病棟にいる妊婦に電話で伝えた。妊婦側は機器のスピーカーから「トク、トク―」という心音を聞くことができる。
感染患者を受け入れる同病院では、妊婦も他の感染患者と同様に隔離病棟に入院する。診察室のベッドや分娩台のそばに置いて使う従来型の分娩監視装置を置く代わりに、iCTGを活用している。黒田医師は「感染した妊婦との接触を最小限に減らしながら母胎の管理ができる。離れていても赤ちゃんの元気な様子がタイムリーに分かるのは、妊婦にも医療者にも有益」と話す。
同病院がiCTGを導入したのは、コロナ前の19年。地域に分娩施設のない妊婦が小樽まで通う負担を軽減したいと、隣町の余市協会病院で月2回開設する出張助産師外来に機材を持ち込んだ。昨年11月から4カ月間、国の実証事業にも参加した。切迫早産の傾向がある妊婦に貸し出し、自宅で計測されたデータを医師が確認し、来院の必要性を相談した。妊婦12人が利用し、「通院の負担が減り、安心につながった」と好評だった。
2019年1月にiCTGを製品化したベンチャー企業「メロディ・インターナショナル」(高松市)によると感染拡大した20年以降、大阪や京都、沖縄などの計125病院(道内7病院)が導入。遠隔診療以外にも活用の幅が広がり、院内や自宅療養中の感染妊婦に使う例が増えている。
黒田医師は「基本は対面での健診や診療だが、先進の医療機器をうまく併用すれば、医療の地域格差やコロナの収束が見えない中でも、生み育てやすい環境づくりにつなげられる」と話している。
取材・文/根岸寛子(北海道新聞 東京報道記者)
この記事に関連するタグ
What’s New
- 妊娠・出産
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- 妊娠・出産
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク