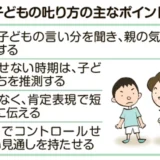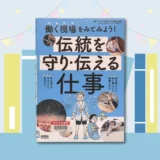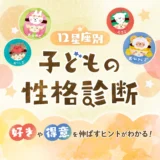たんの吸引15分おき「自分でこなすしか」 医療的ケア児と家族へのサポート道半ば 暮らしやすい地域社会づくり急務


岡部緋良理さんが三女依茉ちゃんのたんを吸引する
たんの吸引や人工呼吸器などを必要とする子どもを示す「医療的ケア児」。日常的に医療支援を必要とする子どもを育てる家族は、負担も大きい上、社会から孤立しやすいです。最近、医療的ケアが必要な子どもが亡くなり、母親が保護責任者遺棄致死容疑や殺人容疑で逮捕される事件も起きています。医療的ケア児と家族を支えるために社会はどう変わるべきなのか、当事者や専門家の声を探りました。
酸素ボンベとベビーカー きょうだいと出掛けたいのに
「たんの吸引は15分置き。30分も空けられません。車でデイサービスに送迎をする際も、停車中に吸引します」。札幌市北区のパート岡部緋良理(ひらり)さん(31)は三女の依茉(えま)ちゃん(1)のケアについてこう語る。

「医療ケアが必要な子どもとの生活を知ってほしい」と話す岡部緋良理さんと三女の依茉ちゃん
依茉ちゃんは、生後1カ月の時に染色体異常の5pマイナス症候群と分かった。1万5000~5万人に1人という難病だ。生後5カ月で退院し、訪問看護や訪問診療を利用しながら、夫婦でケアを担う。
手足は自由に動かせるが、自発呼吸が難しく気管切開をしたため、たんの吸引が必要だ。食事は経管栄養で、ミルクを鼻のチューブから与えている。専用ボトルを使って1回30~40分ほどかかる。外出先であげる場合は、シリンジで1回あたり55㏄ずつ計4回で、作業は40~60分ほどだ。
ミルクは1日5回、時間を決めて与える必要があり、最後の5回目は午後11時。すべての作業を終え、岡部さんが寝るのは午前0時ごろ。午前5時には1回目の経管栄養が始まる。たんの吸引も、依茉ちゃんが寝ている間に1~2回は必要だ。「ずっと寝不足の状態が続いているのがつらい」と岡部さんは話す。
酸素ボンベとベビーカー きょうだいと出掛けたいのに
依茉ちゃんが生まれて生活は一変した。外出はミルクの時間を避けるようになった。酸素吸入をしていて外出時は酸素ボンベを持ち歩く必要があり、ベビーカーは必須だ。
6歳の長女と3歳の次女を連れて遊びに行きたいと思っても、屋内の遊び場はベビーカーで入れない場所が多く、諦めるしかない。2人が外遊びをする時は、夫婦どちらかが連れて行き、どちらかは自宅で依茉ちゃんのケアをする。家族で旅行することも難しい。
働き方も変わった。依茉ちゃんは生後10カ月の時に、重症児のデイサービス施設(児童発達支援事業所)に行き始めた。現在は週3、4回利用し、その間、岡部さんはパートで働く。出産前はフルタイムで働いていたが、医療的ケア児が通える保育園は数も定員も少なく、預かりも7時間程度。フルタイム勤務は諦めた。

「死につながる」恐怖 片時も気を抜けず
夫は仕事が忙しく、平日の帰宅は午後7時過ぎ。泊まりがけの出張もあり、時には3人を1人で見る「ワンオペ」ものしかかる。夕飯準備前に依茉ちゃんを入浴させ、のどを切開して入れている「気管カニューレ」を固定するバンドを交換するが、「カニューレが外れると死につながる」といい、片時も気を抜けない。「疲労困憊(こんぱい)しても体調を崩しても、自分でこなすしかない。気合で乗り越えています」
岡部さんは、同じような悩みを持つ友人とつながりたいと昨年2月に、インスタグラムにアカウント(@ema.okb)を開設した。現在、フォロワー約130人とつながって悩みを共有している。
医療的ケア児の子どもが亡くなり、母親が逮捕された事件について、「孤独を感じて気持ちに余裕がなくなる人はいると思う。事件を人ごととは思えない」と話す。「家族には医療行為をする責任感や緊張感がある。家族が休息を取るために利用できるレスパイトの施設はまだ少ない。もっと身近で利用しやすい環境があれば」と切に願う。
孤立しないために 家族の会「Team Dosanco」
北海道医療的ケア児者家族の会「Team Dosanco」代表の看護師小山内淳子さん(48)=札幌市手稲区=も、事件の背景に思いを巡らせている一人だ。「孤立し、必要なサポートにつながれなかったことが、悲しい事件につながったのではないか」と考える。

医療的ケア児の家族会代表の小山内淳子さん(左)。夫と協力しながら、長男のケアを担う
染色体異常の18トリソミーで、肢体不自由の長男大和ちゃん(5)を育てている。孤立を防ぐために、同じ境遇の親同士がつながるのが大事だと思い、2021年に家族会を作った。
親は、子どもに医療的ケアが必要であることを親族に受け入れてもらえなかったり、人の目を気にして外出を避けたりして、「ストレスを抱えながら孤立しやすい」と小山内さん。
「家族だけで」と思いがち 誰もが支援につながる環境を
小山内さん自身も、夫婦ともに親は遠方にいるため頼るのは難しい。夫の大地さん(39)は「家族だけで面倒を見なくてはいけないと気負ってしまいがち」と語る。

小山内さんが長男との外出時に使うバギー。人工呼吸器やバッテリー、痰の吸引器など多くの荷物が必要だ

小山内さんが自宅で使っているたん吸引器
サービスや施設には地域差があり、支援につながれない家族もいる。小山内さんは「病院からの退院時に、誰もが精神面なども含めたサポートをする人とつながることができるシステムがあってほしい」と願う。
小山内さんは、町内会のイベントや東京の家族会の集まりに、大和ちゃんを連れて積極的に外出している。「医療的ケアが必要な子が、地域で暮らしていることを分かってほしい。それが医療的ケア児が暮らしやすい環境づくりにつながるからです」と言葉に力を込めた。
医療的ケア児死亡と家族をめぐる事件
たんの吸引が必要な娘=当時8歳=を自宅に放置して窒息死させたとして、昨年11月に兵庫県姫路市の30代の母親が、保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕された。今年1月には福岡市で娘=当時7歳=の人工呼吸器を外して窒息死させたとして、40代の母親が殺人容疑で逮捕された。
全国に2万人、15年間で倍増 支援は自治体の「責務」
こども家庭庁によると、全国の医療的ケア児は約2万人。この15年間で倍に増えた。このうち道内には約700人いると推計される。一方で、預け先が足りないなど支援は十分とは言えず、家族の負担が課題となっている。

家族や子どもたちへの支援が重要視され、2016年の児童福祉法改正で、自治体の努力義務に、21年の「医療的ケア児支援法」制定で「責務」となった。
現在、医療的ケア児が受けられる主なサービスは国の制度が定めた①居宅介護②短期入所③訪問看護―などで、これに各自治体が独自でサービスを上乗せをしている。
例えば、札幌市は昨年10月から、国と北海道の補助を受け、家族の休息を目的とした「レスパイト(休息)事業」を独自で開始。訪問看護の医療保険の上限を超えて年24時間、自己負担なしで利用できるとした。

医療的ケア児支援法施行から3年半、障害福祉・医療サービスを提供したり、相談に乗ったりする事業所は増えつつある。
ただ、こうした事業所は高齢者や成人の障害者の利用が多く、実際に対応できるかどうかは医療的ケアの種類や子どもの年齢にもよる。
対応できる事業所は…道と札幌市「把握していない」
このため、道や札幌市は、医療的ケア児に対応できる事業所数について「把握していない」とする。その上で、道子ども家庭支援課は「支援が足りない地域があることは認識しており、医療的ケア児と家族へのアンケートや市町村を通じて困り事を聞き取っている」、札幌市障がい福祉課は「(支援が)充足しているとは考えていない。レスパイト事業を拡充するなどして対応したい」と言う。
北海道医療的ケア児等支援センター(札幌市手稲区)の土畠智幸センター長は「(道内の中では事業所が多い)札幌市内では、必要なサービスを利用できない状態ではないが、短期入所を使いたい時に空きがないといった声は聞く」と話す。
地域間格差大きく 人も施設も足りない
一方で、小規模市町村が多い道内では、地域間格差も激しい。道の23年度調査(札幌市を除く)では家族が抱える課題として、対象412人のうち16%が「ひと時も離れられない(「まあ、当てはまる」を含む)」、43%が「家族の急病や急用時の預け先がない(同)」と答えた。
道内から広く患者を受け入れる旭川医科大病院周産母子センターの長屋健教授は「地方は資源が圧倒的に足りない。短期入所施設がなかったり、訪問看護や居宅介護は受けられるが職員に小児の経験が不足していたりする地域もある」と指摘。「行政が支援者をサポートし、法律や制度にも地方の実情を反映させる必要がある」と話している。
母親にケア負担偏り 7割「睡眠不足」
さらに、ケア負担が母親に偏る課題も顕在化している。厚生労働省が20年に公表した医療的ケア児の生活実態に関する調査報告書によると、主な介護者は94%が母親だった。回答者のうち7割は「慢性的な睡眠不足」「いつまで続くか分からない日々に強い不安を感じる」、半数以上が「社会から孤立していると感じる」と答えている。
昨秋以降、事件の報道が相次いだ際には、交流サイト(SNS)に、「家族の負担や孤立について広く知られるべきだ」などの投稿が相次いだ。
子どもが家族に依存せず生きられる社会に
土畠センター長は「サービスを使っていても悩みを抱える家族はいて、なぜこうなったのかを考察する必要がある」と説明。その上で、「ケアを親がずっと担わなければと思う必要はない。医療的ケア児が家族に依存せず、生きられるようにすることが重要だ」と話している。
この記事に関連するタグ
What’s New
- 子育て・教育
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- 子育て・教育
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク