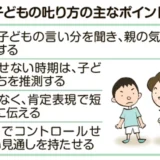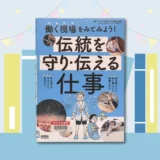連載「男性と育児その先へ」
乏しい父親への支援 育児学び相談できる場がない


子育てパパサークル「ここちち」の活動について話す岩渕代表(左端)らメンバー
子育てをする男性たちから、男性が育児の知識を学び、悩みを共有・相談できる場を求める声が上がっています。男性の「産後うつ」などメンタル不調のリスクが指摘される一方で、父親の育児支援を行う自治体は全国で6.5%にとどまり、サポートは乏しいのが実態です。父親支援を行う団体は「男性を育児の当事者と捉えた支援が必要」と指摘しています。
パパサークル設立 子育て楽しく
「育児について知ることで、楽になることがたくさんある。同じ父親が学べる場を増やしたい」。0~6歳の子ども3人を育てる札幌市の岩渕聖矢さん(32)はそう話します。現在小1の長女がイヤイヤ期だった2歳の時、イライラして怒ってしまうことに悩み、育児の知識を得ることの大切さを実感しました。2021年に「子育てパパサークルここちち」を設立し、勉強会や親子イベントを開いています。
元道職員。子育てをきっかけに保育士資格を取り、市内の保育園に勤めました。昨秋に第3子が生まれ、今年3月で退職し、今は「主夫」として自営業の妻(33)と共に育児に専念しています。
サークルを設立したのは、道職員時代に同僚男性が育児で心身に不調を抱えて休職し、父親同士が悩みを話す場の必要性を感じたことがきっかけでした。「身近にお父さん同士が集まるイベントはなかった。お父さん同士が知り合える機会があれば、もっと普段の子育ては楽しくなる」と語ります。
自治体「ニーズ分からない」 支援実施6.5%
一方、自治体の支援は十分ではありません。国立成育医療研究センター(東京)が全国の自治体を対象に行った20年度の調査(回答は837自治体)で、主な対象を父親とする育児支援を実施したのは54自治体と6.5%にとどまりました。実施をしていない理由では「支援ニーズが分からない」が最多でした。他方で、必要性を感じている自治体は約7割を占めました。
同センターが全国の3歳以下の子どもがいる父親1360人を対象に行った22年のウェブアンケートでは、社会や制度に対して感じる「モヤモヤ」を聞いた設問(複数回答可)で、「父親の育児支援が整っていない」「父親が子育てしやすいような制度・環境が整っていない」がいずれも4割を超えました。
法律の規定なく
母子保健法では母子健康手帳交付や母親から相談を受けることが義務付けられているのに対し、父親の支援を定めた法律はありません。
3月に第1子が生まれた札幌市の銀行員倉西章夫さん(38)は「父親が育児について周囲に相談する機会はほとんどない」と話します。子どもの誕生に合わせて有給休暇を使い、2カ月休みました。夫婦とも育児で睡眠不足になり、家族で利用できる民間の「産前産後ケアホテルココカラ」を計3回、利用しました。休息が目的でしたが「抱っこで手が痛い」「ミルクを飲みたがるだけ与えていいのか」など、育児の悩みを助産師に話すことができました。「相談できて良かった。父親にも育児支援は必要だと思う」と感謝しています。
求めなくても行き届く支援を
母親が参加する育児教室について、多くの自治体は「父親の参加や相談があれば対応する」としています。ただ、母親の参加者が圧倒的に多く、父親たちは参加のハードルが高いと感じているといいます。
自治体や企業、市民と協働し「父親支援を当たり前にする文化作り」などを目指す「Daddy Support(ダディサポート)協会」(東京)の平野翔大代表理事は、父親支援が乏しい背景について「父親は母親の支援者として位置づけられ、育児の当事者として捉えられてこなかった」と指摘しています。父親自身が自ら困っている事を認識できていないことが多いため、「自治体はニーズ調査から始めることが最も大事。その上で、母子手帳配布時に父親向けに資料を用意するなど、父親が自ら求めなくても行き届く形で支援策を講じてほしい」としています。
道内自治体 遊び方学ぶ講座や「父子手帳」独自配布
道内の自治体は、父親が育児に関わるきっかけ作りなどを目的に事業を展開しています。

札幌市が昨年、開催した父親向けの子育て支援イベント
札幌市は、父親による子育て推進事業「サツパパ」を2020年から実施。サイトを立ち上げ、子育てを楽しむヒントを紹介しています。各区の保育・子育て支援センターに来てもらうきっかけになればと22年から各区で年1回、0~1歳の子どもと父親を対象に講座を開いています。子どもとの遊び方を学ぶほか、父親同士の交流の時間も設け、今年は8月から順次開催予定です。
各区のセンターではほかに月数回、離乳食などの育児について学ぶ教室を開いています。対象は限定していませんが、ほとんどは母親です。市子育て支援推進担当課は「ニーズの把握が十分にできていない中、父親に特化した教室を同じペースで開くのは難しい」と話しています。
ほかに帯広市や苫小牧市は、母子健康手帳とは別に、父親向けに妊娠中の女性の体の変化や育児の情報をまとめた「父子手帳」を独自に配布しています。通常は母子健康手帳の配布と同時に母親に手渡していますが、苫小牧市は「夫婦で取りに来るケースが増えている」としています。
取材・文/石橋治佳(北海道新聞記者)
この記事に関連するタグ
What’s New
- 子育て・教育
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- 子育て・教育
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク