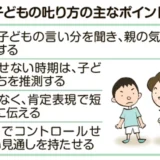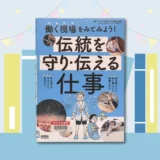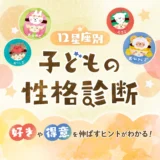<聴覚過敏、知っていますか?>「運動会で走りたい」 ピストル音が苦手な子どもたち

「聴覚過敏」は、「ドーン」と響く打ち上げ花火、イベントなどでスピーカーを通じて流れる音楽や司会の声など、特定の音に苦痛を感じる障害です。ちょっとした配慮があれば、救われる人がいます。当事者の思いや、広がりつつある支援の取り組みを取材し、2回に分けて報告します。
「運動会に出たくない」。5月下旬、札幌市の小学1年男児(6)は、母親(45)にそう訴えた。理由はピストルの音。幼稚園のころから競技用のピストル音が苦手で、競技の時は両耳をふさいでいた。

ヘッドホンのような形状の「イヤーマフ」。周囲の不快な音を抑え、耳を守る効果がある
10日後の開催を控え、母親は学校に相談。担任教諭からは、耳をふさぐヘッドホン状の耳当て「イヤーマフ」の使用や、ピストルを使わない競技への参加を提案された。だが、男児はイヤーマフを付けて参加するのを嫌がった。
当日、男児は運動会を母親と校舎内で見学した。校庭でピストル音が響くと、窓際から奥の教室へ逃げ込んだ。走るのが好きという男児は「(ピストルの)音がなかったら出たかった」と打ち明ける。
母親は「ピストルの代替手段を学校に検討してほしいという気持ちもあった」が、要望は伝えなかった。イヤーマフで参加している児童もおり、「わがままだと思われたらと考えると言えなかった」。

札幌・新発寒小で使われている電子ピストル。後ろのスピーカーから耳に優しい音が出る
火薬式のピストルの代わりに電子ピストルや笛などを使う学校はある。帯広・川西小は2017年から電子ピストルに切り替えた。曽我真澄教頭は「音量などが調整できるのが利点。ピストル音をこわがる児童にも適している」。札幌・新発寒小も児童の安全などのため、19年から変更した。「ピストル音が苦手な聴覚過敏の児童にも対応できる」とする同小の佐々木洋介教頭は「札幌市内で対応している学校は少ないのでは」と指摘。札幌市教委も「どのくらいの学校が切り替えているか情報はない」という。
ピストル音を苦手とする聴覚過敏の子どもは少なくない。東京都北区を中心に活動する発達障害児の親の会「グラン・ブーケ」は21年、運動会のピストルに関するアンケートを実施した。きっかけは「学校にどのように相談したらいいか分からない」という会員の声だった。
代表の渡辺香織さん(50)は「自分の子どものために学校全体に関わる変更を要望するのは、『過剰な要求』で、逆に子どものためにならないのでは、と悩んでしまう」と説明する。「ピストル音を我慢することで子どもの成長につながるなどと考える学校もあり、保護者との間でズレが生じることも少なくない」という。

グラン・ブーケが作成した冊子。帯広・川西小など電子ピストルを使っている小学校の対応も紹介している
親の会は、アンケート結果や体験談をまとめた冊子「しってほしい 聴覚過敏と運動会のピストルの音のこと」を21年に発行した。冊子では、苦手な音やその苦痛の度合いには個人差があるとし、「社会生活を営む上でも大きな影響を与える」と記載。帯広・川西小など学校の対応例や体験談も紹介している。渡辺さんは、「この冊子を利用して、学校と保護者の意思疎通が円滑に進めば」と願う。
文科省「遠慮せず申し出て」
障害者差別解消法は、行政機関、学校、企業などに、障害者の活動を制限する障壁を可能な限り取り除く「合理的配慮」を義務づける。内閣府が公表している「事例集」では、聴覚過敏で運動会のピストル音でパニックを起こすかもしれないケースについて、ピストルの代わりに「笛・ブザー音・手旗などによってスタートの合図」をしたと記載している。
小学校での代替手段の使用について、札幌市教育委員会(札幌市教委)は「(聴覚過敏の)子どもの実態に応じて対応するよう各学校に任せている」という。文部科学省特別支援教育課は「絶対にピストルを使わなければならない理由や事情があるとか、代替手段の導入が難しいのでなければ、遠慮せずに申し出たら、合理的配慮の提供を受けられるのでは」と話す。
法に定められているのに、合理的配慮への理解が広がっていないと指摘するのが、北大大学院教育学研究院の安達潤教授だ。聴覚過敏など感覚過敏について、「関心を寄せる人は詳しくなるが、関心ない人は聴覚過敏(という障害)があることすら気づかない」と強調。「ピストル音が苦手な子でも運動会に参加できるようにするにはどうしたらいいか、一緒に参加する子どもたちに解決策を考えさせるように支え促すのが教育なのでは」としている。
発達障害「聴覚つらい」55%
国立障害者リハビリテーションセンター研究所(埼玉県所沢市)の和田真・発達障害研究室長によると、なぜ、聴覚過敏を含む感覚過敏になるのか、そのメカニズムは、はっきり分かっていない。聴覚過敏の場合、「脳神経系の調節がうまくいかないことで、自分の聞きたい音に集中できなかったり、ざわざわとしたノイズが気になったりしてしまう」という。

国立障害者リハビリテーション発達障害研究室の和田真室長
発達障害の中でも自閉スペクトラム症のある人の60~90%が何らかの感覚の問題を持っていると言われている。
和田室長らは2018~19年に、発達障害のある人431人に調査を実施した。当事者にとって最もつらいのは「聴覚」にまつわるもので回答(415人)の55%を占めた。視覚、触覚、嗅覚はそれぞれ10%程度だった。苦手な音としては、①子どもの泣き声や電子音など特定の音②大音響③突然生じた(ように感じられる)音、など。人によって苦手とする音が異なるのも特徴だ。
発達障害の人だけが感覚過敏というわけではない。「一般の人でも10~20%程度、感覚過敏の人はいるという研究もある」と説明する。
取材・文/稲塚寛子(北海道新聞記者)
この記事に関連するタグ
What’s New
- 子育て・教育
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- 子育て・教育
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク