育児中の母親の栄養支える 札幌保健医療大生が隔月カフェで献立提供


ニポカフェに参加し食事を楽しむ母親たちと子どもを世話する学生
子育てで忙しく、自分の食事は後回し―。そんな女性たちの栄養不足を補いたいとの思いで、札幌保健医療大学の栄養学科の学生20人でつくるサークルが取り組みを始めた。札幌市東区のカフェを隔月で1日貸し切り、考案した献立を親子に提供するイベント「nipocafe(ニポカフェ)」。学生が子どもの世話をし、母親がゆっくりと食事を味わえる場づくりを目指す。
「作りたてを温かいうちに食べるなんて本当に久しぶり」。4月中旬、カフェ「つぐの間」。札幌市西区の主婦、川浪愛美(まなみ)さん(33)は、白身魚のソテーを口に運びつつ、笑顔を見せた。食事中は学生が1歳の長男、5カ月の次男をあやしてくれていた。

札幌保健医療大の学生が考案、調理した献立。右下がカブのポタージュ
ニポカフェは札幌保健医療大の管理栄養士を目指す学生有志20人と教員2人、「つぐの間」を経営する合同会社「LinC(リンク)」が4月に始めた。サークルの顧問で同大准教授の金高(きんだか)有里さん(41)らが昨年、市内で実施した食事イベントを発展させた。午前と午後の計2回、定員各4組で、学生が考えた食事を用意し、レシピも手渡す。献立の一部は後日「つぐの間」のメニューにも加え、来店者が注文できるようにする。
この日は午前、午後で大人8人、子ども7人が訪れた。献立は白身魚のソテーのほか、アスパラのミモザサラダ、カブのポタージュ、ナガイモ食パン。メニューを考えた大学4年の阿部汐華(しおか)さん(21)は「家庭で簡単に作れて、素材の味が生きるように薄味を心がけた」と話す。
活動の背景には、産後の女性の栄養バランスの崩れへの懸念がある。金高さんが昨年、13歳以下の子を育てる母親87人に市内で調査したところ、「食事を食べないこと(欠食)はあるか」との問いに3割が「たまにある」、2割が「よくある」と回答。また、食事の悩みとして半数が「栄養の過不足があるか分からない」と答えた。
金高さんは「産後の女性は栄養が失われた状態で、育児をスタートさせる。お母さんの元気が、子どもの元気にもつながる。バランス良く適切な量を食べる大切さを伝えていきたい」と力を込める。(有田麻子)
心の健康 バランス良い食事から
産後、心身の不調に悩まされる女性は少なくない。栄養不足が心の健康に与える影響について、手稲渓仁会病院(札幌)の精神保健科部長、白坂知彦(ともひろ)さん(45)に聞いた。
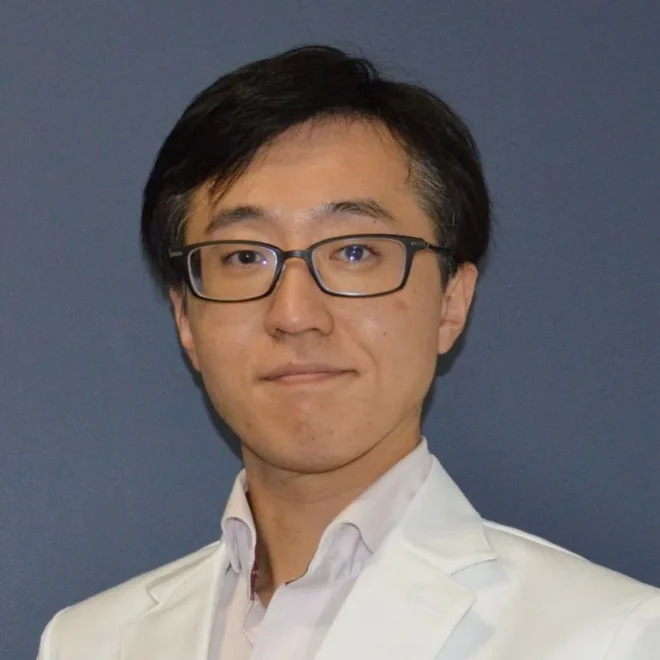
白坂知彦さん
栄養不足やバランスの悪い食事がうつ症状をもたらすのでは、と記した論文は複数あります。例えば、野菜や魚介類、オリーブ油を使う地中海式の食生活を送る人は、そうでない人に比べてうつ病の発症率が低いという海外の報告のほか、鉄分不足と産後うつのリスクの関連を示す研究などです。
「幸せホルモン」と呼ばれ、心の安定を保つ脳内の神経伝達物質「セロトニン」の原料になっているのが、必須アミノ酸の一つであるトリプトファンです。大豆や肉類などのたんぱく質に含まれ、食事から摂取することが求められます。
心の健康にはバランスの良い食事に加え、適度な運動も大切です。子どものためにも親は自分自身を愛し、いたわってあげてください。
この記事に関連するタグ
What’s New
- ニュース
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- ニュース
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク













































