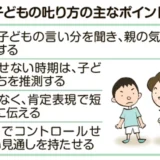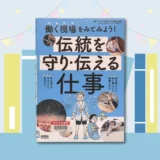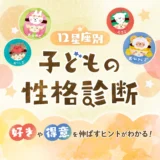持ち物点検、親の役割は 「手伝う」6割強 「対応は母」にストレス


学校の持ち物をかばんに詰める小学生
新学期が始まって1カ月余り。子どもの忘れ物は親にとっては悩みの種だ。家事や仕事に多忙な合間を縫って持ち物の準備や確認に追われたり、忘れ物を学校へ届ける親も少なくない。「子どもが忘れ物をしないようにしなければ」と責任を感じる母親もいる。子どもの忘れ物に、親はどう対応したらいいのか、関係者や専門家に聞いた。
「私が至らないために、申し訳ありません」。後志管内のアルバイトの女性(42)は4月、長女(12)がプリントの一部を提出していないことを指摘する担任教諭からの電話を受けて、ひたすら謝った。
「全部は防げない」
「母親の私が気を付けなくては」と思い、前日のうちにプリントを全部出すよう毎日声をかけ、自分も目を通した。それでも、忘れ物はなくならない。長女に声をかけ忘れたり、長女が学校で口頭で指示されたものを忘れることもある。「私がどんなに頑張っても、忘れ物は全部は防げない」とため息をつく。
発達障害の可能性がある2人の子を育てる札幌の自営業の女性(39)も、担任教諭から子どもが忘れ物をしないよう対応を求められたことがある。ただ、ある時から持ち物チェックはしないことにしたと言う。自身のストレスが大きくなったからだ。「膨大なプリント類を漏らさず確認して、忘れ物をさせないようにするのは無理。子どもが自力でできるよう、学校で指導してもらいたい」と話す。
女性は仕事で多忙のため、学校に対して全ての連絡を夫の携帯にするよう頼んでいたが、その多くは自分に来ると言う。「『(父親ではなく)お母さんに言って、何とかしてもらおう』という先生たちの意識を感じる」と苦笑する。
ベネッセコーポレーション(岡山市)が小学生の母親を対象に行った2017年の調査では、月に数回以上忘れ物をする子どもは49.2%。親が子どもの持ち物の用意を手伝う割合は62.8%に上り、子どもではなく「母親が用意する」という家庭も13.1%あった。
学校現場では、子どもの忘れ物をどう捉えているのだろうか。空知管内のある小学校長は「子どもたちが自分で用意できるよう指導しているが、低学年の間は保護者がサポートするよう、保護者会で呼びかけている」と言う。保護者会の出席は母親が大半。忘れ物の多い子がいた場合、連絡帳や電話で「お母さんに対応を求めることが多い」という。
「父は仕事」根強く
子どもの小学校入学時に親が仕事と子育ての両立に悩む「小1の壁」の問題に詳しいキャリアカウンセラーの曽山恵理子さん(東京在住)は「学校側には今も『父は仕事、母は家庭』という意識や文化が根強くある」と指摘する。「PTA活動も同様ですが、持ち物の確認や宿題の丸付けなど、父親がしても良いことを『お母さんが(やってください)』と伝えられることが多い」と話す。
「持ち物の管理は、あくまでも子どもの役割です。親は子どもを『支援する』ことはあっても、そこに『責任』を感じる必要はない。持ち物チェックを厳しくして子どもを萎縮させるのではなく、子どもの情緒の安定に寄り添うことを大切にしてほしい」とアドバイスしている。
取材・文/酒谷信子(北海道新聞記者)
この記事に関連するタグ
What’s New
- 子育て・教育
- ALL
Editor's pick up
Ranking
- すべて
- 子育て・教育
Area
道央
道南
道北
道東
オホーツク